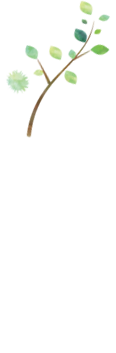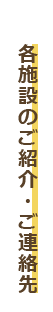お知らせ
Information
認知症 財産管理 後見人
年齢を重ねるにつれて、お金の管理に不安を感じる方は少なくありません。
特に認知症の症状があらわれると、通帳や契約のことが分かりづらくなり、思わぬトラブルにつながってしまうこともあります。そんなときに心強いのが「成年後見人制度」です。家族にお願いするのがよいのか、それとも専門家に頼るべきか、迷うこともあるかもしれません。
本記事では、認知症による財産管理の課題と、成年後見人制度の基本から選び方のポイントまでをやさしくご紹介します。
認知症とお金の問題は、なぜ起こるのか?
認知症になると、少しずつ判断力や記憶力に影響が出てきます。そうなると、お金の管理がうまくいかなくなり、思いがけないトラブルが起こることもあります。
認知症になると、どんなお金のトラブルが起こる?
認知症になると、物事の判断が難しくなったり、記憶があいまいになったりすることで、お金の使い方にも変化が見られるようになります。例えば、同じ物を何度も買ってしまったり、予定外の出費が増えたりするケースもあります。
また、お財布や通帳を自分でどこに置いたか忘れてしまい、「誰かが持っていったのでは?」と感じてしまうこともあります。
家族が本人の通帳や不動産を管理するのはOK?
認知症の家族の通帳や不動産を「代わりに管理したほうが安心」と考えるご家族は多いですが、実は注意が必要です。たとえ親子でも、法律の手続きを通さずに勝手に預金を引き出したり、不動産の手続きを進めたりすることはできません。お金の管理に関わるときは、事前に家庭裁判所を通じて後見人を立てるなど、きちんとした方法を取ることで、家族みんなの安心につながります。
「成年後見人制度」とは?基本からやさしく解説
成年後見人制度は、認知症などで判断がむずかしくなったときに、暮らしに必要なお金や手続きを安心して進められるよう支えてくれる制度です。
成年後見人制度の基本を知っておこう
成年後見人制度は、認知症や知的障がいなどで判断がむずかしくなった方を、法律の面から支える制度です。例えば、介護サービスの契約や預金の管理など、暮らしに関わる大切な手続きを本人に代わって行えるようになります。
成年後見人制度でできることの一例:
- 預金の出し入れや通帳の管理
- 介護施設への入所手続き
- 医療に関する契約など
ただし、介護のお世話をしたり、掃除や買い物を代行したりすることは制度の対象外です。あくまで「法的な支援」を行うための仕組みです。
成年後見人と任意後見人の違いをスッキリ整理
成年後見制度には、状況に応じて使い分けられる「2つのタイプ」があります。いずれも、認知症による財産管理や契約手続きをサポートするための制度です。
|
種類 |
始まるタイミング |
後見人を決める人 |
特徴 |
|
法定後見 |
判断力がすでに低下しているとき |
家庭裁判所 |
状況に応じて、後見人・保佐人・補助人が選ばれる |
|
任意後見 |
まだ元気なうちに契約する |
本人(契約によって) |
あらかじめ信頼できる人を選べる |
「将来が心配だけど、誰に頼むかは自分で決めたい」という方には、任意後見も検討してみましょう。
成年後見人ができること・できないこと
成年後見人には、法律に基づいてできることと、できないことがあります。ここではその違いをわかりやすく整理してみましょう。
成年後見人が主にできること:
- 預金口座の管理や振込、引き出し
- 介護サービスや施設入所などの契約
- 医療に関する手続き(入院契約など)
- 税金の申告、年金の申請
- 家庭裁判所への財産報告
成年後見人ができないこと(制限されること):
- 孫や親族に自由におこづかいを渡すこと
- 本人の財産を使ってのリフォームや贈与
- 投資や資産運用(基本的にはNG)
成年後見制度は、本人の財産や権利をしっかり守ることを目的とした制度です。
自由度は少ないかもしれませんが、「大切なお金が不当に使われてしまう心配を減らせる」という意味では、大きな安心につながります。
成年後見制度を利用するまでの流れ
成年後見制度を利用するには、まず家庭裁判所に申し立てるところから始まります。
必要な書類や手続きの流れ、かかる費用の目安をあらかじめ知っておくと、準備もしやすくなりますよ。
申立てはどこにする?誰ができる?
成年後見制度を利用するには、ご本人が住んでいる地域を担当する「家庭裁判所」に申し立てをします。申立てができる人は、次のように決まっています。
- ご本人
- 配偶者
- 四親等以内の親族(子・孫・兄弟姉妹・いとこ など)
- 市区町村長(ご家族がいない場合など)
申し立て先の裁判所がわからないときは、お近くの家庭裁判所に問い合わせれば教えてもらえます。
申し立てに必要な書類と準備
申し立てをする際には、あらかじめいくつかの書類をそろえる必要があります。中でも重要なのは、医師による診断書です。「後見・保佐・補助」のどれが適切かを判断します。
【主な必要書類】
- 医師の診断書(家庭裁判所指定の書式)
- 戸籍謄本、住民票
- 財産の内容がわかる書類(通帳コピー、不動産の情報など)
- 申立書(家庭裁判所のHPから入手可能)
まずは主治医に相談し、診断書の準備から始めるとスムーズです。
成年後見人はどうやって決まるの?
成年後見人は、家庭裁判所が調査や面談を通して決めます。
申し立て時に「この人にお願いしたい」という候補者を出すこともできますが、最終的な決定は裁判所が行います。
選ばれる人の例:
- ご本人のご家族や親しい方
- 弁護士や司法書士などの専門家
候補者に不安がある場合や、ご家族が遠方に住んでいる場合などは、専門家が選ばれることもあります。
状況によっては、後見人を見守る「後見監督人」が一緒に選ばれることもあります。
審判が下りるまでの期間
申し立てから後見人が選ばれ、実際に活動を始めるまでは、早ければ1か月ほどで進みます。ただし、準備が不十分だったり、本人の面談や医師の鑑定が必要になると、もう少し時間がかかります。
【目安となる期間】
- スムーズに進んだ場合:約1か月
- 面談や書類の追加が必要な場合:2〜3か月
- 鑑定や調整が多い場合:半年ほどかかることも
書類をしっかりそろえて、余裕をもって動くのがおすすめです。
利用にかかる費用はどれくらい?
成年後見制度を利用する際は、以下のような費用が発生します。申立ての内容や地域によって多少変わることがありますが、大まかな目安は以下の通りです。
|
費用の種類 |
金額の目安 |
|
収入印紙 |
約3,400円(申立手数料含む) |
|
郵便切手 |
約3,000〜5,000円 |
|
鑑定料(必要な場合) |
約10〜20万円 |
その他にも、戸籍謄本や診断書の取得費用もかかります。ご本人の収入が少ない場合などは、公的な支援制度を利用できることもありますので、自治体に確認してみると安心です。
家族が成年後見人になる?専門職に頼む?選び方のポイント
成年後見人を誰にお願いするかは、ご本人やご家族の暮らし方や気持ちに関わる大切なことです。
身近な家族にお願いするか、専門家に頼るか、それぞれの良さや注意点を知っておくと、安心して選びやすくなります。
家族が成年後見人になるメリット
信頼しているご家族が成年後見人になると、普段の様子や考え方をよく分かってくれている分、安心してまかせやすいのが大きなメリットです。健康のことやお金のことを、よく知らない第三者に話さずに済むのも、心が落ち着く理由のひとつです。また、専門家にお願いすると発生する毎月の報酬も、ご家族であれば抑えられたり、場合によってはかからないこともあります。気持ちの面でも、費用の面でも負担を軽くできる方法といえるでしょう。
家族が成年後見人になる注意点
ご家族が成年後見人になると、財産や生活のことについて定期的に家庭裁判所へ報告をする必要があります。書類の準備や手続きには時間がかかり、慣れないと大変に感じることもあります。また、一度後見人になると、基本的には途中で辞めることは難しくなります。さらに、親族どうしの関係によっては「なぜあの人が?」と不満が出てしまい、思いがけずトラブルに発展することもあるため、事前に話し合いをしておくことが大切です。
専門職後見人に任せるとどうなる?
司法書士さんや弁護士さんなどの専門家にお願いすれば、法律や手続きのことに詳しいため、複雑な書類づくりや裁判所への報告などもスムーズに進めてもらえます。ご家族だけでは対応がむずかしい場面でも、頼れる存在となってくれるでしょう。ただし、専門家にお願いすると、毎月2〜5万円ほどの報酬が必要になるケースもあります。ご家族の負担を減らしたいときや、信頼できる人が周りにいない場合には、専門職後見人は安心できる選択肢のひとつです。
まとめ
認知症によるお金のトラブルは、ご本人だけでなく、ご家族にとっても気がかりなことが増えてしまうものです。通帳や不動産の管理、介護施設の手続きなど、暮らしのなかで必要な判断や対応には、少しずつ手助けが必要になっていきます。成年後見制度は、そうした日常を法律の面から支えてくれる仕組みです。制度の内容や特徴を知っておくことで、いざというときの備えにもつながります。